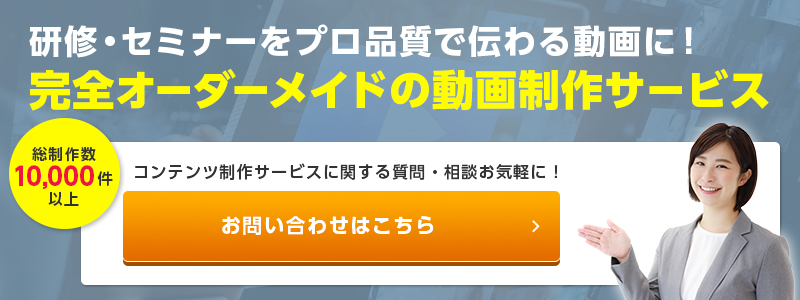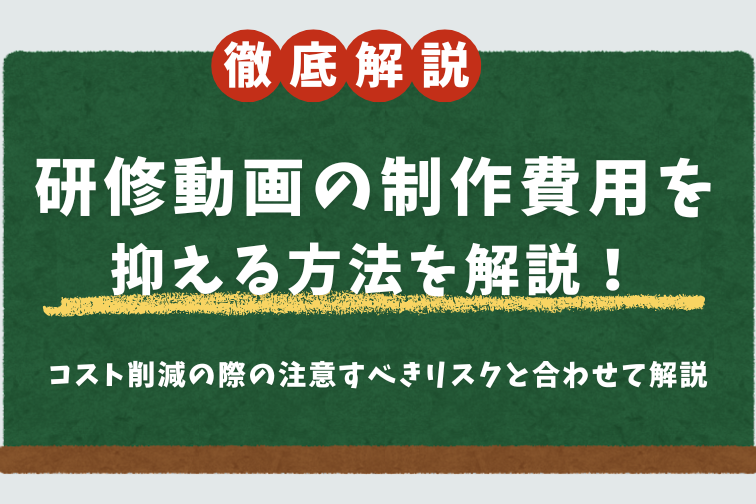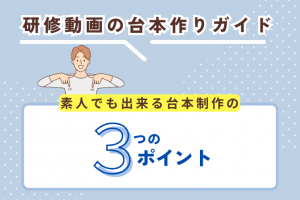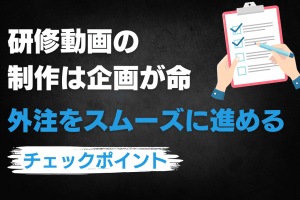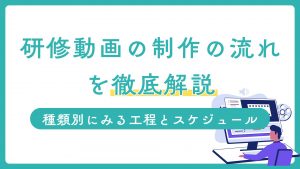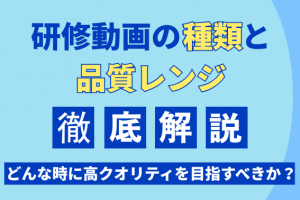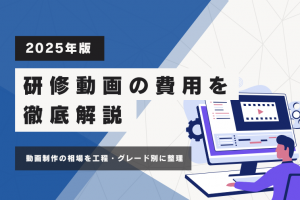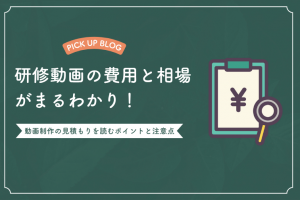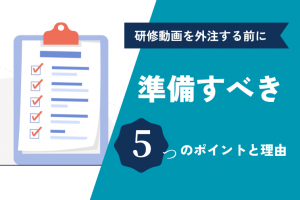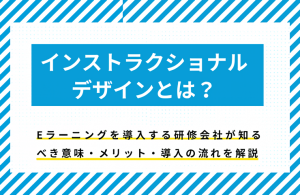「研修動画を作りたいけど、できるだけ予算は抑えたい…」
実際、研修動画は一部の工程を社内で対応する(=内製化する)ことで、外注費を減らし、研修動画の費用削減につなげることができます。
たとえば企画構成や撮影、編集など、工程ごとに分けて自分たちで対応する方法です。とはいえ、安易に削減すると、品質や効果に影響が出ることもあります。
そこで今回は、どの部分を内製化すれば、どれだけ削減できるのか、そしてその際のリスクについてもご紹介します。
研修動画は普通の動画と違う
まず押さえておきたいのは、研修動画は通常のPR動画やYouTube動画とは違い、「教育効果」を出すための専門性」が求められるということです。
単純にスマホやZoomで録画すればよいわけではありませんし、かといって高い費用をかけて美しい映像や派手な演出・エンタメ性を追求すればよいというものでもありません。
研修動画において本当に重要なのは、
- 内容やテーマに関する専門知識の理解
- 視聴者が理解しやすい構成
- 知識が定着するための演出
- 集中力を途切れさせないテンポ
といった「専門知識+学習設計」の視点が必要になります。
たとえば、安全研修であれば労働安全衛生法や業務手順の正確性が重要ですし、医療研修であれば解説に用いられる専門用語の正確さや、映し出される技術や手順の正しさが特に重要となります。
こうした背景知識なしでは、誤った情報や不適切な表現が動画に残ってしまうリスクがあります。
研修動画制作は「企画構成」「撮影」「編集」「ナレーション・BGM」など複数の工程で成り立ち、それぞれの設計や品質が受講者の理解度や研修効果に直結します。
このため、見積書も複雑になりやすく、同じ「10分の動画」でも依頼内容や品質レベルによって費用感が大きく変わります。
結果として、研修動画の費用削減を考えるには、まずこの構造を理解することが欠かせません。
詳しい見積書の読み解き方は、こちらの記事「研修動画の費用と相場がまるわかり!動画制作の見積もりを読むポイントと注意点」でご紹介しています。
研修動画のどこを社内で制作するとどれだけ安くなる?
研修動画コスト削減のカギは“内製化”
費用を下げる一番シンプルな方法は、外注範囲を減らす=内製化することです。たとえば、10分程度の尺でスライド+ナレーションの研修動画を制作会社に全外注するとします。
スライド制作と、ナレーターによるナレーションをセットで依頼し、内容に合わせた演出や効果音も追加した場合、費用はおおよそ20万〜30万円が目安です。
では、この中から一部の工程を内製化すると、どれだけ費用を削減できるのでしょうか?
工程別の削減額をシミュレーション
たとえば、前述の条件(10分尺・スライド制作+ナレーター・演出込み/費用20万〜30万円)で考えた場合、次のように工程を内製化すれば、その分の外注費を削減できます。
| 内製化する工程 | 削減できる目安費用 | コメント |
|---|---|---|
| 企画構成 | 約3万〜5万円 | 社内で研修内容やシナリオをまとめれば、その分の企画費は不要。ただし構成の質によって理解度が変わるため注意。 |
| スライド制作 | 約5万〜10万円 | 社内で資料を作ればコスト削減。ただし見やすさ・デザイン性・視覚的な演出は外注より落ちやすい。 |
| 撮影(今回は該当なし) | – | このケースではスライド型なので該当なし。実写がある場合はさらに削減可能。 |
| 編集 | 約5万〜6万円 | 本来10〜20万円かかるレベルのスライド編集も、不要部分のカットや簡単なテロップ入れなどを社内で対応できれば、外注費をおさえられる場合があります。結果として、5〜6万円程度に収まるケースもあります。 |
| ナレーション | 約3万〜10万円 | 社内の人間が読むことで削減できる。ただし聞き取りやすさや発声の安定感に差が出る。 |
合計:最大で約16〜31万円削減できるケースも(※複数工程を内製化した場合)
あくまで今回の金額は一例です。制作内容やクオリティの要件によって変動します。詳しい工程別の相場や費用感については、
こちらの記事「【2025年版】研修動画の費用を徹底解説~動画制作の相場を工程・グレード別に整理~」をご覧ください。
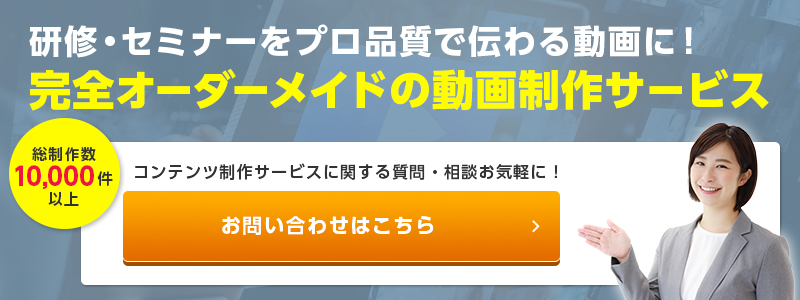

でも注意!内製化にはリスクがある
逆にコストが増えるケース
- 情報の間違いによる録り直し
例:最新の社内規定を入れ忘れ、動画の内容が古いまま完成 → 撮影もスライドも作り直し になり、撮影費と編集費が倍に。 - 社内撮影の失敗
例:照明不足で映像が暗く、受講者から「見づらい」とクレーム → 再撮影+再編集で外注 費が上乗せ。
これらの理由で、一回で済むはずの制作が複数回に及んでしまえば、当然、コストは増えてしまいます。
しかも、発生しているのは社内人件費のため「追加コスト」として認識されにくいのが厄介な点です。
結果として、作り直しを繰り返せば、外注する以上にコストが膨らむケースもある、ということを心得ておきましょう。
クオリティ低下による評価ダウン
- 聞き取りづらいナレーション
社内の人が担当したが、抑揚がなく単調で眠くなる → 研修効果が薄れる。 - 台本の構成不足
内容の順序や説明のつながりが不十分で、受講者が理解しにくい → 再編集や説明資料の追加が必要。 - スライドの見栄え不足
デザインが素人感丸出しで、受講者の集中が続かない。
音声が聞き取りづらく、内容の流れが分かりにくく、さらにスライドの見栄えも悪いとなれば、受講者の理解度は大きく損なわれます。
単に「動画を作った」だけでは、教材としての役割を果たせない恐れがある点を忘れてはいけません。
内製化に潜む落とし穴
このように、研修動画を内製化する場合には、コストの増大や品質の低下といったリスクがつきまといます。そもそも研修動画の制作は、専門業者が存在することからも分かるように、なかなか片手間で行えるものではありません。
慣れていない担当者が本業の業務時間を削って制作に取り組んでも、仕上がりが不十分で結局やり直しになるケースも少なくありません。品質の低いものを作り直し、完成日がどんどん遅れ、担当者も疲弊していく……というのが最悪のシナリオです。
仮に立派な動画が完成したとしても、その裏で通常業務が滞っていれば本末転倒です。内製を検討する際は、「コスト」「品質」に加えて「社内リソース」という観点でも慎重に判断する必要があります。
削減すべき/すべきでない工程の見極めを誤ると、作り直し=コスト増加になりがちです。迷ったら「内製で品質を保てる工程だけ残し、要となる工程は最初からプロに委ねる」ほうが、総額もスケジュールも安定します。どこを内製化しても大丈夫かは、事前にプロへ相談して判断するのが安全です。
コスト削減は、まず“内製化できる体制”を整えることから
片手間ではなく、しっかりと体制を整えよう
台本作成・スライド制作・撮影・編集――どの工程も専門知識が必要です。
「誰が、どの工程を、どれくらいの時間を使って担当するのか」を最初から明確にし、体制を整えておくことが、内製成功の第一歩です。
体制が整えられない場合は、いったんプロに相談
社内に十分な人材や時間を割けない場合は、無理に内製化を進めるよりも、制作会社に相談した方が安心です。
どの工程を外注すべきか、どの部分なら社内で対応できるかを客観的にアドバイスしてもらうことで、無駄なコストや労力を避けられます。
「内製化をしたいけれど、何から始めたらいいか分からない」ときも相談を
「自分たちでできるところはやりたいけど、どこから手をつけていいか分からない」というケースも少なくありません。
その場合も、まず制作会社に相談することで、
- 内製化できる範囲
- 外注した方が効率的な工程
- 内製化に必要なスキルや準備
といった具体的な基準を得られます。結果として「ここは外注」「ここは内製」という最適なバランスを見つけやすくなります。