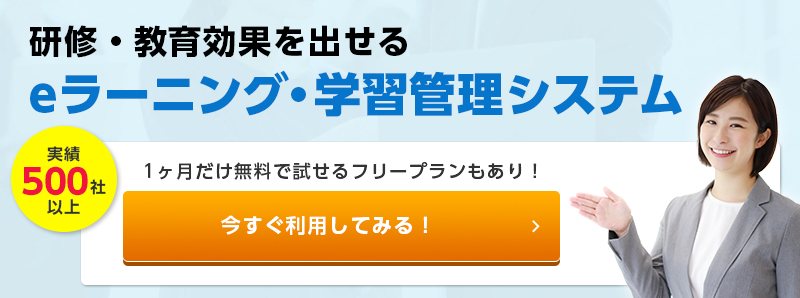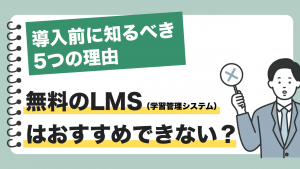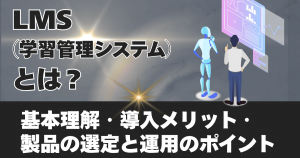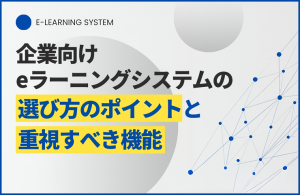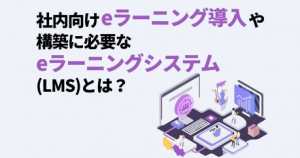DXの流れや多様な働き方の浸透により、研修会社にとってもeラーニングシステムの導入は重要な選択肢となっています。対面型の研修では対応しきれないニーズに応えられるだけでなく、時間や場所に縛られない学習体験を提供できる点が大きな魅力です。
しかし、導入後に「思ったより使われない」「現場の負担ばかりが増えた」といった声もよく耳にします。成功のカギは、eラーニングシステムを“単なるツール”として導入するのではなく、“研修の仕組み”として活用する視点を持つことです。
この記事では、研修会社がeラーニングシステムを導入する際に注意すべき3つのポイントを解説します。
- eラーニングシステムを導入時の「目的と活用方法の明確化」
- コンテンツ制作と運用体制をセットで考えるべき理由
- eラーニングシステムを選定する際に見落としがちな注意点
目的と活用方法を明確にしないと失敗する

eラーニングシステムの導入で最も多い失敗例は、「何のために導入するのか」が曖昧なままスタートしてしまうことです。システム導入はあくまで“手段”であり、“目的”ではありません。
目的が明確でないと、現場からの協力も得られず、結局使われない投資になりかねません。たとえば、研修会社がeラーニングシステムを導入する目的には、次のようなものがあります。
効率性の向上
講師や教室の稼働分に依存せず、いつでも販売できるパッケージ型の講座を展開したい複数日程が必要な研修の日数短縮に、知識の提供部分についてはオンデマンドに移行したい、研修購入のオンライン決済、申込人数の管理や出席管理、研修日程の自動メール配信等で事務作業を減らしたい
提供価値の差別化
他社と差別化(日数の短縮、効果の増大)した研修を提供し、営業に活用したい
成果測定の自動化
受講後のテストやアンケートの結果をデータ化し、クライアントへ定量的に報告したい
目的ごとに必要な機能が異なります。受講者の学習ログを活用した分析を行いたい場合は、LMSのデータ出力機能やBI連携が必要になるかもしれませんし、オンライン決済や出席管理、研修とeラーニングの自動的な組み合わせを作る場合は業務フローにあわせた機能が必要に、さらに、管理者、講師、受講者が不便にならないような、ユーザーインターフェースのカスタマイズ性も重要になります。
さらに、社内の誰が主導して導入するのかも明確にする必要があります。教育担当者だけで完結できる内容なのか、IT部門やマーケティングと連携する必要があるのか。プロジェクトの進め方にも大きく関係します。
初期段階で「なぜ今eラーニングシステムを導入するのか?」「5年後、どう活用されていたいのか?」という問いに答えることが、後の混乱を防ぎ、戦略的な導入につながります。
自社に合わせたカスタマイズ性がないと、長期運用で行き詰まる

eラーニングシステムは、「標準機能で十分」と思っていても、「もっとこうしたい」「ここを変えたい」といったカスタマイズのニーズが必ず出てきます。
特に研修会社の場合、クライアント企業ごとに異なる要望に対応する必要があるため、システム側の柔軟性が非常に重要です。
標準機能だけでは対応できない現場の課題
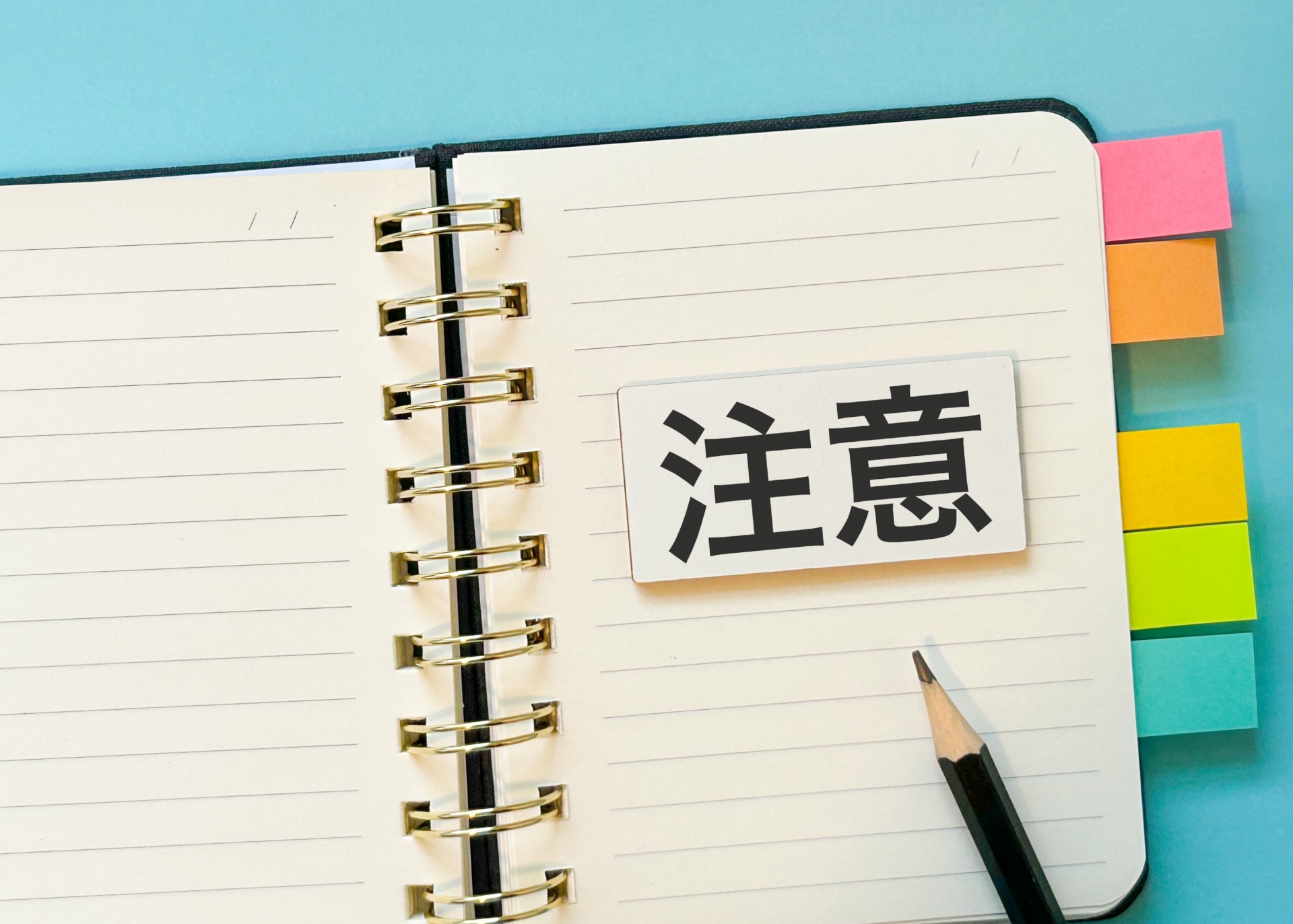
たとえば、以下のような細かい要望が現場から上がることがあります。
- システム内で決済ができるようにしたい(決済システムとの連携)
- リアルタイム×eラーニングを組み合わせた形式でおこないたい(ブレンデッドラーニング)
- 日程調整を効率化できるシステムを組み込みたい
- A社には動画を2本ずつ順番に見せたいが、B社は最初から全教材を開放したい
- テスト問題の出題順をランダムにしたい
こうした要望に標準機能で対応できなければ、運用のたびに手作業が発生し、業務負荷が増大します。また、毎回カスタマイズ対応をベンダーに依頼し、費用や工数がかかるようでは利益率が下がってしまう問題も起きてきます。
柔軟なeラーニングシステムの条件とは?

自社運用にフィットするeラーニングシステムを選ぶには、以下のような観点からカスタマイズ性を事前に見極めることが大切です。
- テンプレートやUIが編集できるか
- API連携で既存の営業管理ツールや顧客管理システムとつなげられるか
- 顧客ごとの受講条件・閲覧制限の設定が簡単にできるか
- 独自ドメイン・SSL対応など必要な機能の拡張が可能か
eラーニングシステムを提供する会社によっては「外部連携やUI変更は一切不可」といったケースもあるため、導入前のヒアリング段階で“どこまで柔軟にカスタマイズできるか”を必ず確認すべきです。
コンテンツと運用体制をセットで考える

eラーニングシステムの導入は、システム選び以上に「どのようなコンテンツを、誰が、どのように制作・運用していくか」が成功の鍵を握ります。eラーニングシステムはあくまで“土台”であり、そこに載せる“中身”がなければ意味をなしません。
研修会社の場合、自社のノウハウを活かした独自教材を開発することが多いですが、次のような課題が発生しやすいです。
- 講師が多忙で動画収録の時間が確保できない
- ナレーション・スライド作成が属人化していて進まない
- 受講者に満足してもらえるようなクオリティのコンテンツが作れない
- 教材の管理がバラバラで受講者によって内容が異なる
こうした課題を回避するには、「コンテンツ制作・更新の体制」をあらかじめ設計しておく必要があります。たとえば、以下のような工夫が考えられます。
- テーマごとに教材責任者を明確にする(例:マネジメント研修はA氏、コンプラ研修はB氏)
- 外注先を活用して、動画を量産できる仕組みを作る
- クオリティが高いコンテンツを作れる外注先を活用する
- インストラクショナルデザイン等を活用し、目的、受講者のレベルと教材の管理を行う
また、受講者からのフィードバックやテスト結果に応じて教材を改善する「PDCA型運用」を行うには、運用担当者が継続的にデータ分析を行う必要があります。つまり、教育部門の中に“デジタル教材運用チーム”を立ち上げることも視野に入れるべきです。
コンテンツは作って終わりではありません。継続的に改善しながら、研修の成果を最大化する運用体制こそが、eラーニングシステム導入の成功を左右する最大の要因です。
eラーニングシステムの選定で「使いやすさ」と「サポート体制」を見落とさない

「何となく有名だから」「導入実績が多いから」といった理由でeラーニングシステムを選定してしまうと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。特に研修会社のように、顧客とのフロントに立つ業務では、“受講者側の使いやすさ”と“管理者側の柔軟性”の両立が重要になります。
受講者の視点では、
- 自分が受講するべきコースがすぐに見つかること
- スマホ・PCのどちらでも違和感なく操作できる
- 進捗や未受講が一目で分かる設計
- 学習通知がリマインドとして機能する
管理者・講師の視点では、
- 機能の多寡よりも、ITスキルがそれほど高くない人でも操作が可能なこと
- エンコードやビットレートといった専門用語がわからなくても、動画をアップロードできること
- 運用時の業務フローに合った画面が設計されていること
- 自動化できる部分については、自動化されていること
とにかく、管理者側はマニュアルやIT担当のサポートがなくてもコンテンツを作り続けられる画面、機能が必要で、ここが複雑だと途端にコンテンツの作成が止まってしまいます。
さらに忘れてはならないのがサポート体制の質です。いくら高機能でも、初期設定でつまずい時や、バグに直面したときにすぐ対応してもらえなければ、現場の不信感が高まり、運用が止まってしまう恐れがあります。
- チャット・電話などの多様なサポートチャネルがあるか
- 導入初期にカスタマーサクセス担当が付き添ってくれるか
- マニュアルやヘルプセンターが日本語で分かりやすく整備されているか
- 機能追加や不具合修正の改善スピードは早いか
- 動画配信流量、ストレージ、ID数の追加、サポート料などの追加費用が明確か
「見た目のスペック」ではなく、「自社にとって使いやすく、困ったときに頼れるパートナーかどうか」が、eラーニングシステム選びで最も重視すべきポイントです。
まとめ

研修会社がeラーニングシステムを導入する際には、以下の3つの観点を押さえることで失敗を防ぎ、効果的な運用が可能になります。
- 目的と活用方法を最初に明確にすること
- コンテンツと運用体制をセットで設計すること
- eラーニングシステムは使いやすさとサポート体制で選ぶこと
これらの視点を持つことで、単なる「IT導入」ではなく、学習体験そのものを改善する価値ある投資となります。失敗しない方法の一つとして、まずは小規模な導入からスタートし、段階的に最適化していくアプローチも検討してみましょう。