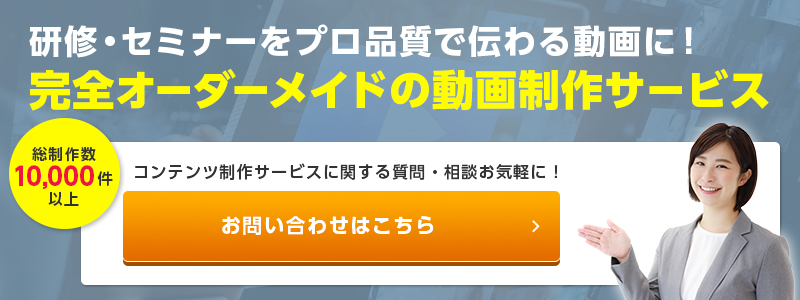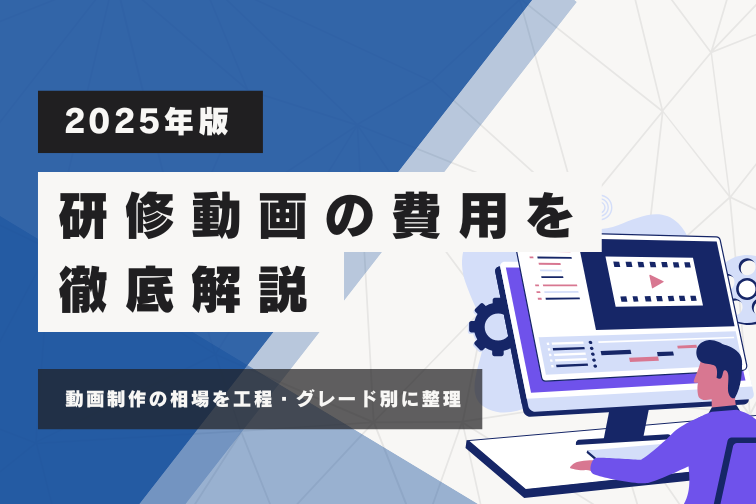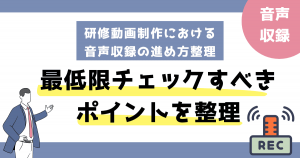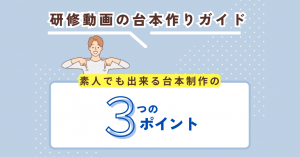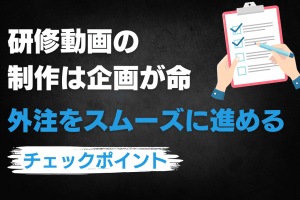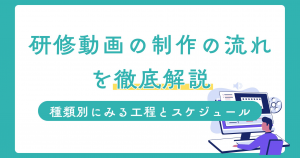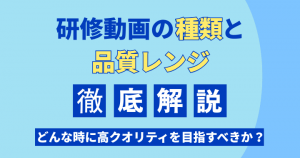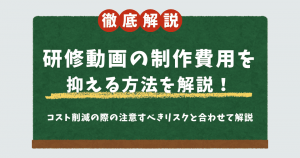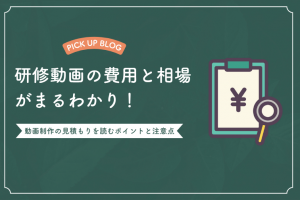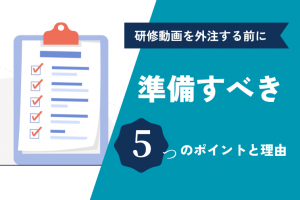研修動画の費用が見えにくい理由とは?
「そろそろ社内研修を動画化したい」「eラーニングでも使える教材を作れないだろうか」そう思って動画制作会社を調べ始めたものの、
- 料金表が載っていない。
- 「まずはご相談を」「ヒアリングのうえお見積もりします」ばかりで、比較が難しい。
- 各社の内容や価格帯にもバラつきがあり、検討が進まない。
そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。
多くの企業が研修動画の導入を検討する際、同じ壁にぶつかります。「比較したいだけなのに、いきなり複数社へ見積もりを依頼するのは現実的ではない」と感じ、検討意欲が一気にしぼんでしまうケースは少なくありません。
実はこうした悩みは、研修動画の導入を検討し始めた企業担当者の間で非常によくあることです。では、なぜここまで、担当者の心理に負荷を与えてしまうのでしょうか?
その背景には、次の2つの要因があります。
理由1:見積もりの内訳が公開されていないことが多い
研修動画の制作は「企画/撮影/編集/ナレーション」など複数工程で構成されていますが、それぞれの費用がどう積み上がっているのかは、Web上に明確に書かれていないケースがほとんどです。
「◯分で◯万円」といったパッケージが用意されていることもありますが、実際には制作内容や目的に応じて追加費用が発生することが多く、比較の判断軸としては使いづらいというのが実情です。
理由2:動画の“目的”や“品質レベル”によって、費用が大きく変動する
一口に「研修動画」といっても、
- 会議室等で1人が喋っているのを撮影した、シンプルな動画
- 図解などのスライドを映しながら、ナレーションで解説する動画社外への配信を前提としたハイグレードな動画(俳優の起用、スタジオ撮影、リッチなアニメーション)
など、目的や使用シーンによって制作工程が分岐し、価格も大きく分かれます。その結果、「相場」と言っても一定の目安が存在しづらく、「結局どの程度の予算を見ておけばよいのか分からない」と感じてしまう要因となります。
そこで本記事では、こうした“見えにくい費用感”をクリアにするために、
- 動画制作にはどのような工程があり、それぞれいくら位の費用がかかるのか?
- 総額で見たとき、どこまでの品質が得られるのか?
- 自社に合った費用対効果の見極め方とは?
といった視点から、研修動画の費用構造をわかりやすく分解していきます。まずは、「動画制作のどこにお金がかかるのか?」から見ていきましょう。
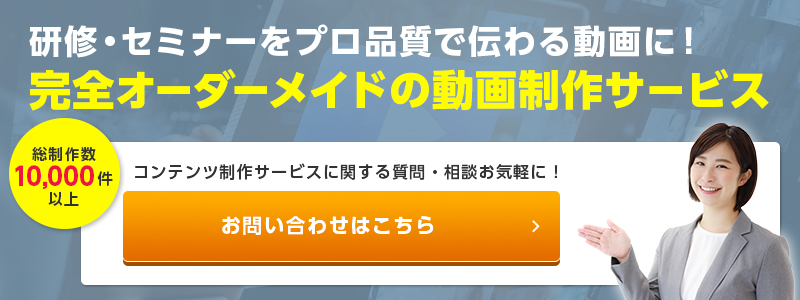

工程ごとの費用目安と、そのグレードの違いとは?
研修動画の制作費用は、企画構成・撮影・編集・ナレーションなど、いくつかの工程に分かれており、それぞれの内容や依頼範囲によって費用が大きく変動します。
本記事では、読者の方に分かりやすく整理するため、各工程を「ライト」「スタンダード」「プレミアム」の、3つのグレードに分類してご紹介します。
すべての制作依頼がこの3パターンにぴったり当てはまるわけではありませんが、この記事では便宜上、以下の基準で分類しています。
ライト 社内でほとんどを制作し、一部だけ外注するケース。
スタンダード 動画のテーマや内容構成は内製し、それ以降の撮影・編集など動画化の工程をすべて外注するケース。
プレミアム どのような動画にすべきか企画段階から相談したい場合や、大きな予算をかけてハイクオリティな仕上がりを目指すケース。あくまで目安ではありますが、「このグレードなら、これくらいのことができる」といった全体像を掴む参考にしていただければと思います。
なお、ここで紹介している相場は、おおよそ5〜10分程度の研修動画1本を制作する場合を想定しています。実際の費用は、内容や尺の長さによっても変動しますが、まずはこの長さを前提に、各工程ごとのイメージをつかんでいただければと思います。
企画・構成
「企画・構成」の費用は、どの範囲まで制作会社に依頼するかによって大きく異なります。
ライト:0円~
社内で構成案(台本)をすべて用意すれば、当然、企画・構成の費用は0円で済みます。ただ、制作会社にそのレビューや修正をお願いする場合は、若干であっても費用が発生します。
制作費を0円に抑えたい場合は、自社で十分に構成案をブラッシュアップしましょう。
スタンダード: 5万円~
制作会社がヒアリングを行い、そこから構成案を一緒に作っていくスタイルです。初期案の提案・フィードバック・調整を含めて、5万〜10万円前後が目安となります。
ただし、ヒアリングに際しては、依頼側が依頼内容を十分に整理しておく必要があります。
どのような動画を制作したいのか、誰に向けて、何を目的として、どのような流れで解説したいのか、こういった点が曖昧なままヒアリングが行われた場合、制作会社から出てくる構成案や台本が希望するものとミスマッチになる恐れもあります。
何度も作り直しになれば、前述の価格感に収まらなくなるため、その点は気を付けましょう。
プレミアム:20万円~
よりクオリティの高い教育動画を制作するため、構成設計に入る前段階で目的の整理や視聴者像の設定(ペルソナ作成)など、通常はスタンダードプランで依頼側が行う上流工程を、制作会社が引き受けます。
この段階から制作会社のディレクターやプランナーが参加し、演出やスライド構成の方向性も含めて設計するため、費用は20万〜30万円程度になることが多いです。
撮影
撮影にかかる費用は、機材の規模・撮影体制・キャスティング・場所によって大きく変動します。
ライト: 5万円~
カメラ1台を用いた簡易撮影で、場所は社内の会議室を使用する場合が多いです。制作会社に撮影のみ依頼する場合でも、半日程度のスケジュールで5万〜10万円前後で収まることがあります。
機材は三脚付きの業務用カメラ1台と簡易照明程度、スタッフも1名で対応するようなケースが該当します。
スタンダード:15万円~
カメラ2〜3台での撮影を行い、半日〜1日かけてしっかり撮影する場合、15万〜25万円程度が目安です。
スタッフも2〜3名体制となり、一般的な実写型の研修動画であれば、このスタンダードプランで対応できるケースがほとんどです。
ただし、スタジオを利用するのか、依頼側のオフィス内で撮影するのか、またオフィス内撮影の場合に照明器具が必要かどうかといった条件によって、金額が前後する可能性があります。
プレミアム:50万円~
スタンダードを超える品質、たとえばテレビ番組に近いクオリティを目指す場合は、スタジオも厳選され、演出の有無やカメラ台数、撮影方法も大きく変わります。
目安としては、50万〜100万円を見ておくとよいでしょう。
さらに、俳優やタレントなどの出演者を起用する場合は、追加費用が発生します。キャスティング手配、演出対応、使用媒体に応じた契約調整などが加わり、内容によっては、100万円を超えるケースもあります。
また、出演者をオーディションで選ぶといったご要望がある場合にも、別途費用が発生します。
編集
編集費用は、どこまでの作業を依頼するかによって幅があります。研修動画では「見やすさ」「テンポ」「理解しやすさ」に直結するため、編集の質が動画の印象を左右することも少なくありません。
ライト:3万円~
最低限のカット編集に加え、簡単なテロップ挿入・BGMの追加といった“最低限の整え作業”のみを依頼するケースです。
収録済みの動画素材をそのまま納品し、「冒頭と最後をカットしてつなげるだけ」など、シンプルな編集であれば、3万〜5万円前後で対応可能な場合があります。タイムラインのつなぎや基本的な明るさ調整などが中心となり、1人のエディターが1〜2日で仕上げる規模感です。
なお、カット箇所やテロップの文言など、依頼側が明確に指示を伝える必要があります。
また、出演者がセリフを間違えすぎる場合、編集業務の負荷が想定を超え、追加費用が発生する可能性もあります。編集費を抑えるためには、本番撮影よりも前に、出演者に十分に練習(リハーサル)をさせておくことも重要でしょう。
スタンダード:10万円~
複数の素材を組み合わせ、テロップ・図表・スライドなども組み込みながら仕上げる編集です。内容の分かりやすさを重視した構成にしたい場合に選ばれるケースで、10万〜20万円程度が相場となります。
ここでいう「スライド」とは、構成段階で作成されたPowerPointなどの資料を指します。編集工程ではそれを映像の流れに合わせて表示させたり、画面の一部に合成したりする作業が発生します。
単純に画像を挿入するだけでなく、テロップとのバランスやタイミングの調整も必要になるため、編集工数は比較的多めになります。
プレミアム:20万円~
編集内容に加えて、多言語字幕・アニメーション・モーショングラフィックスの挿入など、見せ方に強くこだわる仕上げが該当します。
アニメーションとは、たとえば人やキャラクターの動き、アイコンや図解が場面ごとに展開していくといった、視覚的に“動きで伝える”演出を指します。
静止画の挿入に比べて設計や作業に手間がかかるため、20万〜30万円、場合によってはそれ以上かかるケースもあります。
なおPowerPointで設定されたアニメーション(順番に表示、図が動くなど)は、動画編集ソフトにそのまま反映されないことが多く、同じ動きを再現するには、編集工程で新たにアニメーション処理を加える必要があります。
そのため、PowerPoint上で「動きはつけてあるから大丈夫」と思っていても、実際には追加の編集作業が発生することもあるため注意が必要です。
ナレーション・BGM
ナレーションやBGMは、たとえば講師による解説を撮影するだけの動画であれば、あまり必要性はないかもしれません。
しかし、スライド型の教育動画であれば、ナレーションは全体のクオリティを大きく左右する重要な要素となります。
また、BGMや効果音も、適切に使うことで視聴者の理解度や集中力を高める効果が期待できます。
ライト:1万円~
ナレーションを入れず、BGMも無料のフリー素材を使うケースです。編集段階で音量やタイミングの調整だけ行えばよいため、基本的に費用は1万円以内に収まることが多いです。
スタンダード: 3万円~
合成音声(AIナレーション)を使用し、BGMも商用利用可能な有料ライブラリから選定するケースです。ナレーション原稿の整備から、合成音声の生成、タイミング調整までを含めて編集依頼する場合、3万〜10万円前後が目安になります。
合成音声そのもののコストは安価ですが、映像と組み合わせた調整作業を含めると、一定の工数と編集費用がかかります。また、合成音声は、現在の技術であってもまだ、イントネーション、アクセントに違和感が生じます。そこを調整させる場合は、前述の費用が上振れする可能性もあります。
専門用語の多い原稿の場合は、読み間違えも多く発生するという報告もあるため、確実に想定予算に抑えるためには、人間のナレーター(知名度のないナレーターや声優)を起用したほうがかえって安上がりです。その場合の費用は10万円弱くらいになるでしょう。
プレミアム: 30万円~
知名度のあるナレーターや声優を起用する場合です。
キャリアのあるナレーターは、専門的な発声技術に加え、声のトーンや演技表現まで緻密にコントロールされた読み上げが可能となり、視聴者への訴求力が高まります。
また、外販することが前提の教育動画の場合は、有名な声優を起用することが話題性作りにも寄与するでしょう。
ただ、出演料・契約調整などを含め、30万円以上の費用が想定されます。懸念として、音源に関する権利関係が複雑になる場合があります。
ここまで、完成尺10分を想定した費用の目安をご紹介しましたが、もちろん尺が長くなれば、それに比例して費用も増えていきます。
この点もあらかじめ考慮して、予算計画を立てると安心です。
研修動画の形式別・費用感と品質の目安
研修動画の制作費は、動画の形式と品質によって大きく変わります。ここでは代表的な3つの形式について、ライト・スタンダード・プレミアムの目安と特徴をご紹介します。
| 形式 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| スライド×合成音声 | 5万〜10万円程度。スライドは依頼側が用意し、制作会社はナレーションを合成音声で付けるだけ。短納期・低コストだが、声質や抑揚は限定的。 | 10万〜20万円程度。スライド作成も制作会社が担当し、資料の見やすさや構成が改善される。 | 20万〜30万円、場合によってはそれ以上。構成段階から目的や視聴者像を整理し、スライドデザインやアニメーションも充実。BGMや効果音を効果的に追加。 |
| スライド×ナレーター | 10万〜20万円程度。スライドは依頼側が用意し、知名度のないナレーターによる収録のみ制作会社が担当。声質や抑揚は自然で聞きやすい。 | 20万〜30万円程度。スライド制作と知名度のないナレーターによるナレーションをセットで依頼。内容に合わせた演出や効果音も追加可能。 | 30万〜50万円、場合によってはそれ以上。構成・視聴者設計から入り、知名度のあるナレーターを選定。演出・BGM・効果音まで含めた総合的な品質向上。 |
| 講師撮影 | 10万〜15万円程度。カメラ1台で講師を撮影し、簡易的な編集のみ実施。照明・マイクも最小限。 | 15万〜25万円程度。カメラ2〜3台、スタッフ2〜3名で半日〜1日の撮影。一般的な実写型研修動画はこの範囲で対応可能。 | 50万〜100万円、場合によってはそれ以上。テレビ番組に近い品質を目指し、スタジオや厳選機材を使用。演出付き・俳優やタレントの起用も可能(さらに追加費用発生のケースあり)。 |
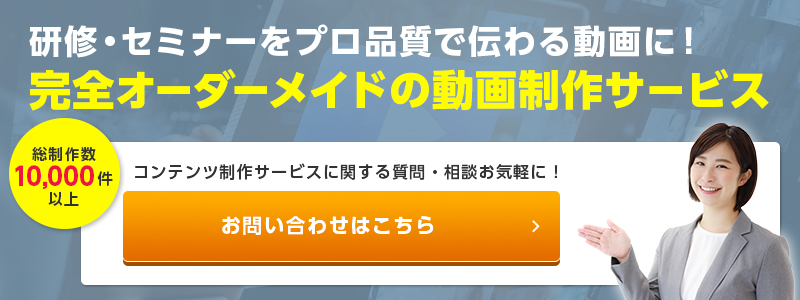

適正な費用対効果を得るために考えるべき3つの視点
動画制作の費用は見積もりだけでは判断が難しく、「高い」「安い」が感覚的になりがちです。しかし大切なのは、“いくらかけたか”ではなく、“その費用で何を得られるか”という視点です。
この章では、研修動画を外注する際に、費用対効果を見極めるための3つのポイントを整理します。
制作目的に対して、必要な品質レベルを明確にする
「社内向けに最低限伝わればよい」のか、「理解度を高めたい」「社外にも公開したい」のかで、求められる構成や演出は大きく異なります。
安さを優先しすぎると、結局“伝わらない動画”になり、本来の目的を果たせず逆にコストが無駄になる可能性もあります。
社内リソースで対応できる工程と、外注すべき工程を見極める
たとえば、構成や撮影は社内で行えるけれど、ナレーションや編集だけはプロに任せたい。
あるいは逆に、社内に構成力はないが撮影は自前で可能——というように、全工程を一括で外注する必要は必ずしもありません。
予算に合わせて「どこまで任せるか」を明確にすることが重要です。
長期的に使える設計かどうかを見極める
一度作った動画が繰り返し使える構成なら、初期費用が高くても結果的にコスパは高くなります。
たとえばスライドの差し替えや章分割がしやすい構成なら、複数の場面で活用しやすくなります。
まとめ:大切なのは「何ができるか?」を知ること
ここまでで、研修動画制作にかかるおおよその金額感をご紹介してきました。しかし、現実にはここまでの単純なパターンに収まるケースばかりではありません。
「自社の場合はいくらになるんだろう?」「どのような作り方をするのが最適なんだろう?」そんな疑問や不安を抱くケースは少なくありません。
実際には、撮影環境や素材の有無、使用する媒体、視聴対象者の特性などによって、最適な制作方法や必要な工程は変わってきます。
だからこそ、発注前に制作会社へ相談してみることはとても有効です。経験豊富なディレクターが、要望や条件をヒアリングし、予算と目的に合わせた現実的な提案をしてくれるからです。
株式会社ITBeeでは、研修動画制作の豊富な実績を活かし、企画段階からのアドバイスや費用の見積もり比較、最適な制作プランの提案まで、発注前でも無料でご相談いただけます。
「動画を作るべきかどうか」という段階からでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
研修動画の費用は一律ではなく、目的や内容、長さ、品質レベルによって大きく変わります。だからこそ、「相場がわかりにくい」と感じるのは当然です。
重要なのは、「この費用で何ができるのか?」という視点を持つこと。
単に安さだけを追求してしまうと、伝わらない内容になったり、使い回せない構成になったりして、かえってコストパフォーマンスが下がることもあります。
費用対効果を見極めるには、「何を目的に、誰に向けて、どれくらいの期間使う動画か?」を明確にすることが第一歩です。
本記事では、グレード別の工程や用途別の相場感をご紹介してきました。ぜひ、「自社にとって必要な投資はどこか?」を見極めるための判断材料としてご活用ください。