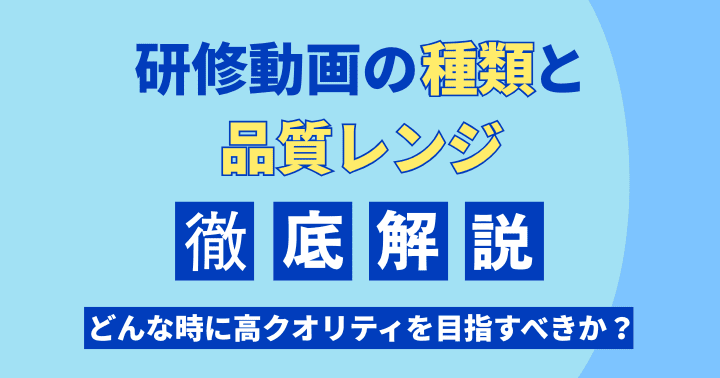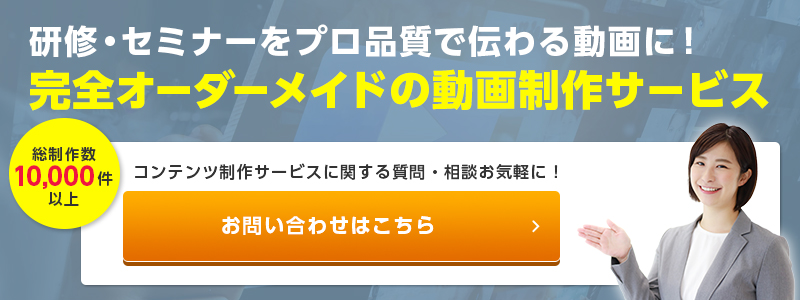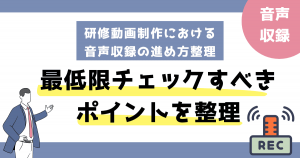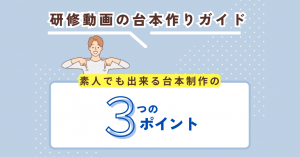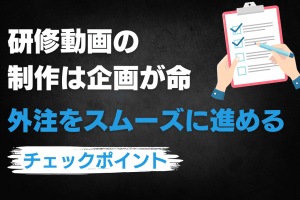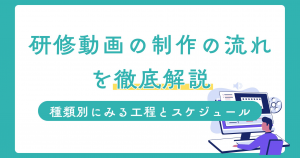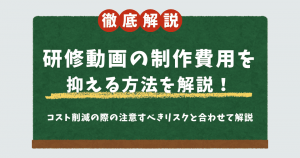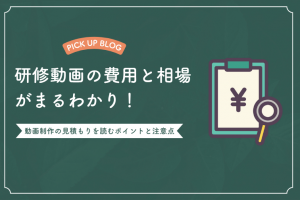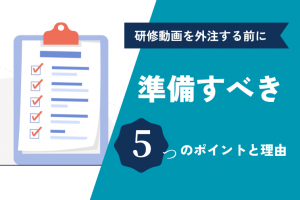近年、社内研修をオンライン化したいと考える企業が急増しています。背景には「全国拠点で同じ教育を実施したい」「人材育成の効率を上げたい」といった課題があります。
そのオンライン化の手段として注目されているのが、研修動画の活用です。ただ、いざ動画による研修を検討してみると、こんな声をよく耳にします。
- 「研修動画って、記録映像みたいなものでは?」
- 「本格的に作るとなると、かなり大掛かりになりそう」
- 「どのレベルを目指せばいいのか分からない」
実際には、研修動画にはいくつかの 表現方法(種類) があり、さらにその中でも “どの程度の手間や工数をかけるか=品質レンジ” が存在します。
本記事では、この「種類」と「品質レンジ」を整理したうえで、どんな場面で高クオリティを目指すべきかを解説し、最後に実際の制作スケジュールの目安をご紹介します。
この記事を読むことで、「自社はどのレベルを目指せばよいか」を見極めやすくなります。
研修動画の種類
まずは、研修動画にどんな種類があるのかを整理してみましょう。大きく分けると、以下の4つに分類できます。
スライド+ナレーション型
PowerPointなど既存の資料を活用し、音声を付けて動画化する方法です。操作マニュアルや業務ルールの共有など、知識をインプットさせたい研修に向いています。コストを抑えやすく、短期間で制作できるのもメリットです。
実写型(講師撮影・ロールプレイ・インタビュー)
講師が解説している様子を撮影したり、営業や接客のロールプレイを撮影して動画化する方法です。表情や動作などをリアルに伝えられるため、臨場感があり、理解や定着につながりやすい特徴があります。インタビュー形式にすると、ベテラン社員のノウハウを共有する場面でも効果を発揮します。
アニメーション/モーショングラフィックス
図解やキャラクターを動かして説明する方法です。複雑な概念やシステム操作の手順を直感的に理解してもらいたい場合に有効です。一度作れば修正や翻訳がしやすいため、長期的に活用したいコンテンツにも向きます。
ハイブリッド型
スライドに実写を組み合わせたり、実写にアニメーションを重ねたりするなど、複数の表現方法を掛け合わせるスタイルです。幅広い受講者に対応でき、メリハリのある動画を作りたい場合に選ばれます。
どの種類を選ぶかで、求められる工程や制作体制は大きく変わります。そして、同じ種類の動画であっても「どの程度の手間をかけるか」によって、仕上がりの品質はまったく異なります。
次章では、その品質レンジをライト/スタンダード/プレミアムの3段階に分けて、具体的なイメージをご紹介します。
品質レンジの違い(ライト/スタンダード/プレミアム)
研修動画を検討する際に重要なのは、「種類 × 品質レンジ」という考え方です。
スライド型・実写型・アニメーション型といった「種類」に加えて、同じ種類の中でも「どの程度の工数やリソースをかけるか」で仕上がりが大きく変わります。
ここではわかりやすく、ライト/スタンダード/プレミアムの3段階に整理して、典型的なイメージをご紹介します。
ライト(簡易版)
| 特徴 | 必要最低限の構成で仕上げる。 |
|---|---|
| 典型例 | 既存のPowerPoint資料にナレーションを追加したスライド動画、会議室で講師をカメラ1台で撮影した実写動画など。 |
| 完成イメージ | 研修教材として安心して使える標準的な品質。 |
プレミアム(ハイクオリティ版)
| 特徴 | 企画から全面的に制作会社が関与し、演出・デザイン性を重視。 |
|---|---|
| 典型例 | スタジオ撮影や高度なモーショングラフィックスを駆使した実写動画、ブランド発信や外販にも使えるハイクオリティ教材、俳優やタレントを起用した映像など。 |
| 完成イメージ | テレビ番組に近いクオリティ。多言語対応・アクセシビリティ対応も視野に入る。 |
このように、研修動画は「種類 × 品質レンジ」の掛け合わせで具体的な完成イメージが決まります。
たとえば実写型でも、ライトなら「会議室で1カメ撮影」、スタンダードなら「複数カメラ+編集」、プレミアムなら「スタジオ撮影+演出」といった具合に幅があるのです。
どんな時に高クオリティを目指すべきか?
品質レンジを理解したら、次に重要なのは「どんな状況で高クオリティを選ぶべきか」という判断です。以下に代表的なケースを整理します。
スモールスタートが向いているケース
- すぐにスタートしたい場合
- 法律改正の影響で更新が頻繁に必要な場合
このようなケースでは、高クオリティを追求すると準備に時間がかかり導入が遅れてしまうリスクや、更新作業が追いつかず中途半端になってしまう可能性もあります。まずはライトまたはスタンダードで小さく始め、必要に応じて追加・改善していく方が現実的です。
高クオリティが必要なケース
- 全従業員に学習させたい重要テーマ(コンプライアンス・情報セキュリティなど)
- 手抜き感のある動画は逆効果。重要テーマこそ見やすく理解しやすい映像にするべきです。
- 大企業ではアクセシビリティ対応(聴覚・視覚障害者への配慮)や多言語対応も求められることが多いです。
- 外販を前提とする場合
- 研修動画を商品として販売するなら、見た目の品質が商品価値を左右します。
- 特殊で希少性のあるコンテンツであれば例外もありますが、通常は低クオリティでは売り物になりません。
実行フェーズの進め方|スケジュールと費用感
研修動画は、品質レンジごとにかかる期間や費用感が異なります。ここでは「ライト」「スタンダード」「プレミアム」の3段階に分けて、代表的な進め方を整理しました。
※いずれの品質レンジでも共通して言えるのは、社内承認のスピードや素材準備の有無がスケジュールの成否を分けるということです。
外注すれば自動的に早く仕上がるわけではなく、台本やスライド、出演者の調整が滞ると進行全体に影響が及びます。あらかじめ準備・合意形成を整えておくことが重要です。
ライト×スライド+ナレーション型
| 期間目安 | 約1〜1.5ヶ月 |
|---|---|
| 費用感 | 10万〜20万円程度(完成尺5〜10分を想定、スライドは依頼側が用意し、知名度のないナレーターによる収録を想定) |
| 流れ | 台本作成(1週)→ナレーション収録(1週)→編集(1〜2週)→公開準備(数日) |
| ポイント | 短納期・低コストで制作可能。制度改正など更新頻度が高いテーマや「まずは試しに1本作りたい」というケースに向いています。ただし、台本やスライド支給が遅れると短納期のメリットを活かせないため、準備を前倒ししておくことが必須です。 |
スタンダード×実写型
| 期間目安 | 約1.5〜2ヶ月 |
|---|---|
| 費用感 | 15万〜25万円程度(完成尺5〜10分を想定、カメラ2~3台、スタッフ2~3名で撮影+編集+テロップを含む) |
| 流れ | 企画・台本作成(2〜3週)→撮影(半日〜1日)→編集(2〜3週)→公開準備(1週) |
| ポイント | 品質・コスト・納期のバランスが良く、多くの企業研修で採用される「標準型」。出演者や会場の調整がボトルネックになりやすいため、承認フローを含めて事前に関係部署と合意形成しておくことが重要です。 |
プレミアム×ハイブリット型
| 期間目安 | 約2〜3ヶ月 |
|---|---|
| 費用感 | 50万円以上(完成尺5〜10分を想定、スタジオ撮影・複数カメラ・演出・アニメーション・多言語対応などを含む) |
| 流れ | 企画・構成(3〜4週)→キャスティング/スタジオ準備(並行2〜3週)→撮影(1〜2日)→編集+演出(3〜4週)→最終調整・公開準備(1〜2週) |
| ポイント | スライドや実写に加えて演出・アニメーションを組み合わせる“ハイブリッド型”。ブランド発信や外販を視野に入れた高品質仕上げで、大企業の重要研修や社外公開を前提とするケースに多い。高品質仕上げほど社内レビュー回数が増えるため、承認スケジュールを並行して確保することが不可欠です。 |
さらに詳しい工程ごとの費用内訳やグレードごとの相場感を知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
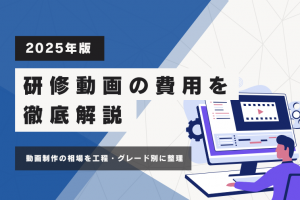
6. まとめ
研修動画には種類と品質レンジがあり、それぞれにメリットと適した活用シーンがあります。
- スライド型/実写型/アニメーション型など、表現方法を選べる
- 品質レンジはライト/スタンダード/プレミアムに分かれる
- 状況によって高クオリティを目指すべきか、スモールスタートすべきかを判断することが大切
- 制作フローはシンプルだが、承認や素材準備が進行の成否を分ける
まずは「自社がどんな動画を求めているのか」を整理し、品質レンジを決めることから始めてみてください。そして、専門会社に相談することで、よりスムーズに実行フェーズへ進めていくイメージができます。
株式会社ITBeeでは、企画段階からの相談・費用感の比較・最適な制作プランの提案まで、発注前でも無料でご相談いただけます。「自社に合った研修動画をどんな形で作れるのか」気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。